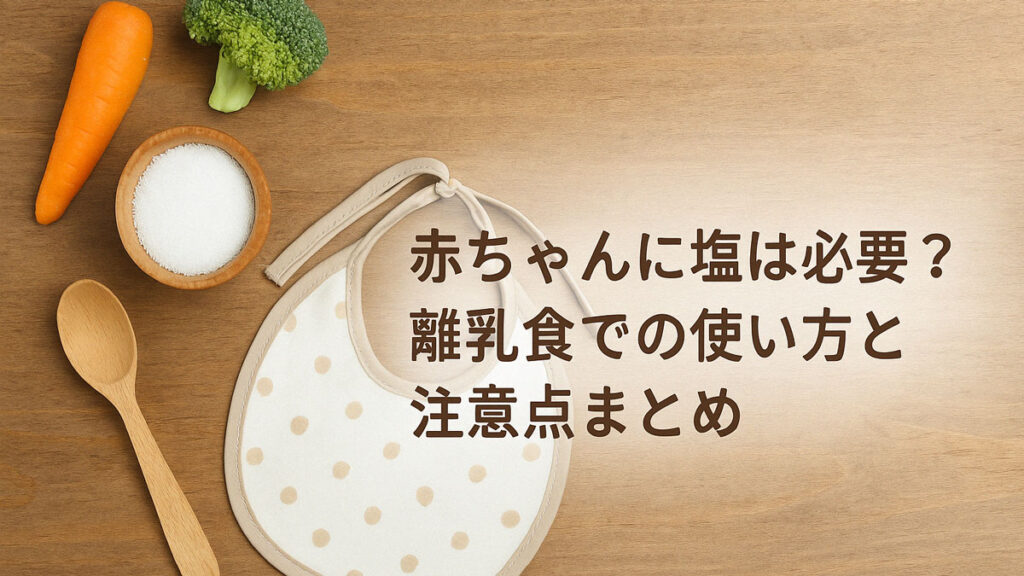
「赤ちゃんの離乳食に塩って使っていいの?」「いつからどのくらい?」と不安に感じていませんか?実は多くの保護者がこの疑問に直面しています。
本記事では、小児科医や管理栄養士の意見をもとに、赤ちゃんにとっての塩の必要性とそのリスクを解説。初期〜後期における適切な使用タイミングや、自然派調味料の選び方、市販ベビーフードの見極め方まで網羅します。
味覚を育てる大切な時期に、なぜ薄味が重要なのかを知ることで、日々の離乳食づくりに自信が持てるようになります。赤ちゃんの健康を願うすべての方に読んでいただきたい内容です。
赤ちゃんに塩は必要?基本の考え方を知ろう

なぜ赤ちゃんには塩分を控えるべきなのか
赤ちゃんの離乳食づくりで、最もよく聞かれる疑問の一つが「塩って使っていいの?」というものです。結論から言うと、離乳食初期~中期にかけては、基本的に塩は使わない方が望ましいとされています。その理由は、赤ちゃんの体がまだ塩分に十分に対応できないためです。
特に注意すべきは腎臓の未発達です。赤ちゃんの腎機能はまだ完全ではなく、塩分(ナトリウム)を十分に排出できるほど発達していません。過剰な塩分摂取は、体内にナトリウムが蓄積し、腎臓に負担をかけてしまう可能性があります。
さらに、塩分を早くから与えることで将来的に「塩味が濃い食事」を好むようになるという研究も報告されています。これは、幼少期の味覚形成に大きな影響を与えることを意味しています。
大人との体の違い(腎機能・成長過程)
大人と赤ちゃんでは、同じ「塩分」でも体への影響が大きく異なります。以下の表をご覧ください。
■ 赤ちゃんと大人の体の違い(簡易比較)
| 比較項目 | 赤ちゃん(0〜1歳) | 大人(成人) |
|---|---|---|
| 腎臓の発達 | 未熟、ナトリウム排出能力が低い | 完成しており機能が安定 |
| 体重あたりの水分量 | 約70〜80% | 約60% |
| 推奨塩分量 | 1g未満(生後6か月以下は0g推奨) | 約6g前後(成人男性) |
このように、赤ちゃんは体が小さく水分量が多いこともあり、わずかな塩分でも体への負担が大きくなります。
特に離乳食初期(生後5〜6ヶ月頃)では、母乳や粉ミルクから必要な塩分を十分に摂取しているため、あえて塩を加える必要はありません。
味付けなしでも食べてくれる理由とは
「塩味がないと味気ないのでは?」と不安に思う方もいるかもしれませんが、赤ちゃんにとっては素材そのものの味が十分な“ごちそう”です。
実際に、かぼちゃやさつまいも、にんじんなど自然の甘みがある食材は、味付けなしでも赤ちゃんに人気があります。これは、赤ちゃんの味覚が非常に敏感で、大人のように強い味付けがなくても「おいしい」と感じられるからです。
また、離乳食期の食事は「栄養を取ること」だけでなく、「味覚を育てる」ことが目的のひとつ。薄味や素材の味に慣れることで、将来的にも健康的な食習慣につながります。
以上のように、赤ちゃんにとって塩は必要不可欠なものではなく、むしろ控えることが健やかな成長につながるという点がポイントです。
次のステップでは「離乳食で塩を使っていいのはいつから?」について詳しく解説します。
離乳食で塩を使っていいのはいつから?
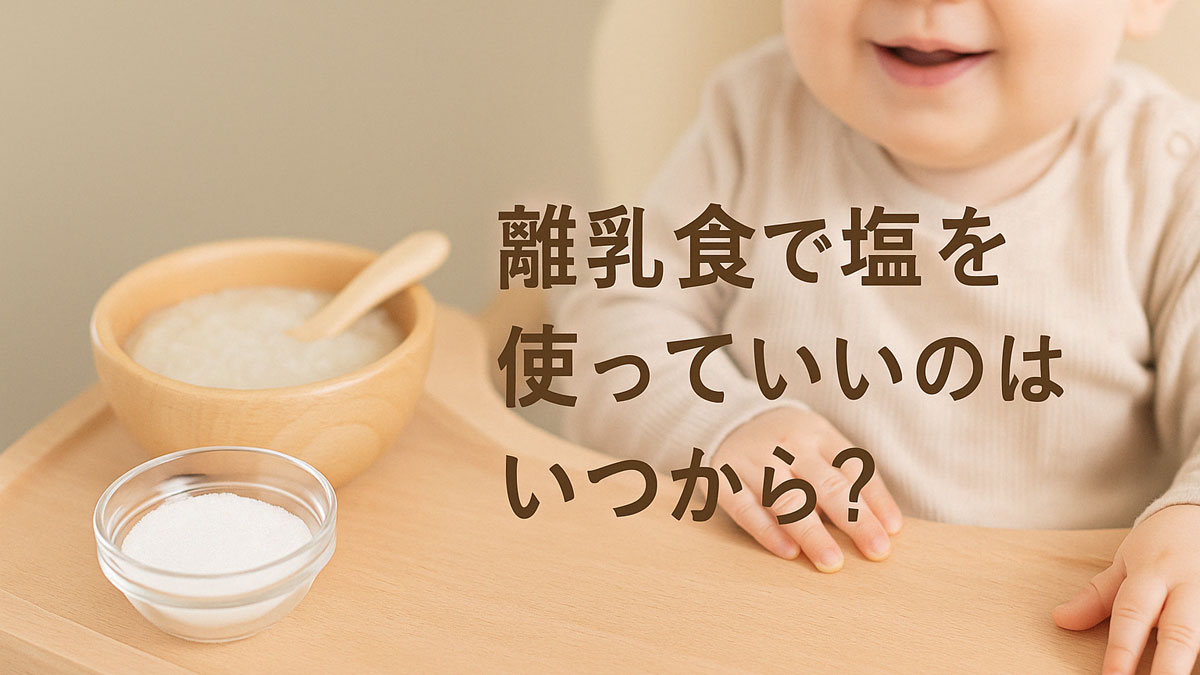
初期・中期・後期の塩使用タイミング
赤ちゃんの離乳食は、おおまかに「初期」「中期」「後期」と3つのステージに分かれます。それぞれの段階で、塩を使ってもよいタイミングや量には大きな違いがあります。
-
初期(生後5~6ヶ月頃)
→ 塩は使用しないのが原則。 母乳や粉ミルクで必要なナトリウムは摂取できており、素材本来の味に慣れさせる時期です。 -
中期(生後7~8ヶ月頃)
→ 基本は無塩。 どうしても味に変化をつけたい場合は、だしや野菜の甘みなどで風味づけをします。 -
後期(生後9~11ヶ月頃)
→ ごく少量の塩使用が可能に。 味付けが必要なメニュー(お好み焼き風、煮物など)の場合、ごく薄味で使用しますが、あくまで「味を感じさせない程度」が基本です。
大人の「薄味」ではなく、「赤ちゃんの薄味」はほぼ無味に近いレベルであることを忘れずに。
離乳食後期でも塩は「ほんの少し」が基本
赤ちゃんが生後9ヶ月を過ぎると、食べられる食材や料理の幅も広がってきます。しかし、だからといって味付けを急に大人と同じようにしてはいけません。
特に「塩」を使う際には、耳かき1杯分以下程度の「ほんの少し」からが基本です。風味をつけたいときには、天然のだし(昆布やかつお節)や、トマトや玉ねぎなどの旨味を活かすことが推奨されます。
また、ベビーフードなど市販品にも「食塩相当量」が含まれているため、併用する際は全体の塩分量を意識することが大切です。
目安量のガイドライン(ミリグラム・食塩相当量)
厚生労働省の「日本人の食事摂取基準(2020年版)」によると、1~2歳児の1日の食塩相当量の目安は3.0g未満とされています。生後9~11ヶ月の赤ちゃんに当てはめると、1日の塩分摂取量は 約1.5g未満が望ましい とされています。
より分かりやすくするため、以下に【赤ちゃんの離乳食期における塩分摂取量の目安】をまとめた表をご覧ください。
■ 離乳食期の塩分摂取目安(食塩相当量)
| 離乳食ステージ | 月齢の目安 | 1日の塩分摂取量の目安 |
|---|---|---|
| 初期 | 5~6ヶ月 | 0g(使用しない) |
| 中期 | 7~8ヶ月 | ~0.3g程度 |
| 後期 | 9~11ヶ月 | ~0.7g程度 |
| 完了期 | 12~18ヶ月 | ~1.0g程度 |
この量は1日あたりの目安であり、1回の食事ではその1/3~1/4程度となるように配慮すると安心です。
また、しょうゆやみそなどの調味料にも塩分が含まれているため、使用する際は原材料表記や栄養成分表示もチェックしましょう。
離乳食での塩の使い方には明確な基準と注意点があります。「いつから?どのくらい?」という疑問には科学的根拠があり、それを知ることで安心して赤ちゃんの食事を用意できるようになります。
次回は、赤ちゃんにおすすめの自然塩や無添加調味料の選び方について、具体的にご紹介していきます。
赤ちゃんにおすすめの「自然派」塩と調味料

自然塩・天日塩・無添加だしなどの選び方
離乳食後期以降になると、ごく少量の塩や調味料を使って風味をつける機会が増えてきます。しかし、大人向けの調味料は添加物や過剰な塩分が含まれることも多いため、素材や製法にこだわった「自然派」の製品を選ぶことが大切です。
たとえば、以下のような塩は赤ちゃんにも比較的安心して使えます。
-
自然塩(天然塩)
→ 海水を原料とし、ミネラル分が豊富。製造過程で添加物を使用していないものを選びましょう。 -
天日塩
→ 太陽と風の力でゆっくり乾燥させた塩で、まろやかな風味が特徴。塩辛さが控えめで使いやすいです。 -
藻塩(もしお)
→ 昆布や海藻の成分を含んでおり、旨味と風味が加わる塩。少量でも味が引き立ちます。
また、塩を使う代わりに無添加の天然だしを活用するのもおすすめです。だしには旨味成分(グルタミン酸・イノシン酸など)が含まれており、塩を使わなくても味に深みを出せます。
「天然だしパック」や「粉末だし」も便利ですが、原材料表示で「食塩」「化学調味料」などが入っていないか確認することが大切です。
市販のベビーフードに含まれる塩分にも注意
便利な市販のベビーフードは、忙しい家庭にとって強い味方です。しかし、中には塩分がやや多めに含まれている商品もあるため、使う際は栄養成分表示を確認しましょう。
以下は、ベビーフード1パック(100gあたり)の食塩相当量の目安です。
■ ベビーフードの塩分量目安(100gあたり)
| 商品タイプ | 食塩相当量の目安 |
|---|---|
| 初期用(5~6ヶ月) | 0.0g~0.1g程度 |
| 中期用(7~8ヶ月) | 0.1g~0.3g程度 |
| 後期用(9~11ヶ月) | 0.3g~0.7g程度 |
1日あたりの適正な塩分摂取量を考えると、1食で0.5gを超えないように注意する必要があります。特に市販品と家庭の手作りを併用する場合、塩分の重複に気づきにくいため、気をつけてあげたいポイントです。
塩の代わりに使える風味づけのアイデア
赤ちゃんの味覚を育てるためには、塩に頼らない風味づけも大切です。以下のような「塩の代替」となる食材や調理法を取り入れることで、栄養と味のバランスをとることができます。
-
野菜の甘み:かぼちゃ、玉ねぎ、さつまいもなどは素材の甘さが強く、塩なしでもおいしい味付けに。
-
香り野菜:にんにくやねぎ(加熱して使用)、しょうがなども風味を引き出すアクセントになります。
-
きのこやトマトの旨味:グアニル酸やグルタミン酸を含み、だしとしても優秀です。
-
昆布・かつお節・干ししいたけのだし:煮出すだけで風味豊かなスープが取れます。
調味料が少なくても、「香り」「甘み」「旨味」を上手に引き出すことで、赤ちゃんは自然な味を楽しむことができます。
自然派塩や無添加調味料を上手に取り入れることは、赤ちゃんの健康を守るだけでなく、将来の食習慣づくりにもつながります。あせらず、素材の力を活かしたやさしい味付けで、赤ちゃんの「おいしい!」を引き出してあげましょう。
専門家の見解|塩の取りすぎと将来への影響

小児科医・栄養士のコメント
赤ちゃんの塩分摂取について、専門家たちはどう考えているのでしょうか。実際に小児科医や管理栄養士は、「乳幼児期の過剰な塩分摂取が将来の健康リスクにつながる可能性がある」と警鐘を鳴らしています。
たとえば、ある小児科医は次のように語っています。
「赤ちゃんの腎臓はまだ未発達で、ナトリウムの排出能力も不十分です。離乳食に調味料を使う際は、素材本来の味を生かし、味つけは極力控えるべきです。」
また、ベビーフード開発にも関わる管理栄養士はこう話します。
「一度“濃い味”に慣れてしまうと、素材の味では満足できなくなります。味覚の基礎が形成されるこの時期だからこそ、塩分を極力控えたやさしい味付けが将来の健康に大きく影響します。」
高血圧・味覚形成との関係
塩分の取りすぎが将来的に影響する懸念の一つが、高血圧のリスクです。日本人は世界的にも塩分摂取量が多く、成人の高血圧率も高い傾向にあります。近年では、子どもの頃の食習慣がそのまま成人期の病気リスクに影響するといわれています。
赤ちゃんの味覚は生後6ヶ月ごろから徐々に発達し、1歳を迎えるころには“好き・嫌い”の基礎が形づくられるともいわれます。ここで濃い味付けに慣れてしまうと、将来的にも塩辛い味を好む傾向が続き、結果として過剰摂取につながる可能性があります。
味覚の形成を支えるうえでも、「うま味」「甘み」「香り」などを活用した自然な風味づけが理想的です。
家庭での塩分管理のコツ
赤ちゃんの塩分摂取量を管理するには、「見える化」と「代替」がカギになります。以下に、実践しやすい管理のコツをまとめます。
■ 家庭でできる塩分コントロールのポイント
| 管理方法 | 内容例 |
|---|---|
| 使用量の見える化 | 調味料の計量は「耳かき1杯=約0.3g」など具体的に意識する |
| 加工品は成分表を確認 | ベビーフード・パン・スープなどは食塩相当量を必ずチェックする |
| 味つけは代替する | 塩ではなく「だし」や「野菜の甘み」で風味をつける |
| 大人の味と分ける | 取り分け調理で、大人用と赤ちゃん用に味つけを分ける工夫を |
特に「大人用の食事からの取り分け」の場合は、先に赤ちゃん用を取り分けてから調味料を加えるなどのちょっとした配慮が、赤ちゃんの健康を守る第一歩になります。
子どもの将来を見据えた食習慣は、今のひとさじから始まります。塩を控えることは味気なさを意味するのではなく、「素材を味わう力」「健康的な味覚」を育てるための工夫です。
過剰に神経質になる必要はありませんが、今日の一食が未来の健康につながっていることを意識して、楽しく食事づくりに取り組んでいきましょう。
まとめ|赤ちゃんの「味覚育て」は薄味から

赤ちゃんの離乳食における塩の使い方は、多くの保護者にとって迷いやすいテーマです。しかし、この記事を通してわかるように、離乳食期は「味覚を育てる大切な時期」であり、塩分は最小限にとどめるべきというのが専門家の共通した見解です。
離乳初期から後期にかけて、赤ちゃんの舌は徐々に成長していきます。素材そのものの味を感じ取る力を育てることが、将来の健やかな食生活に直結します。
特に、現代の食生活では大人でも塩分過多になりがち。赤ちゃんの頃から「濃い味」に慣れてしまうと、それが基準となり、将来的な高血圧や生活習慣病のリスクにもつながりかねません。一方で、薄味に慣れていれば、大人になっても自然な味を楽しめる「味覚力」が育ちます。
■ 離乳期の塩との付き合い方|4つのポイント
以下に、これまでの記事内容をふまえた「味覚育て」に役立つ実践ポイントをまとめました。
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 味付けは素材の風味を活かす | 塩の代わりに、野菜の甘み・天然だし・旨味食材で味を調える |
| 塩の使用は後期以降から | 離乳食後期(9ヶ月〜)でも、ごく少量からスタートし、味を感じない程度にとどめる |
| 市販品の塩分表示を確認する | ベビーフードやパンなど、見えにくい塩分をチェックし、全体の摂取量に配慮する |
| 大人の味から分けて調理する | 取り分け時は、赤ちゃん用に調味前の状態で取り出してから大人向けに味をつける |
これらのポイントを意識するだけでも、赤ちゃんの「味覚育て」はぐっとスムーズになります。
塩を使わないことは「味を我慢させる」ことではない
「塩がないとおいしくないのでは?」と思ってしまう方も多いかもしれません。しかし、赤ちゃんにとっては、かぼちゃの甘み、にんじんの香り、昆布だしの旨味など、塩がなくても感じられる味の世界がしっかりと広がっています。
むしろこの時期に塩味に頼ってしまうことで、本来の味を楽しむ力が育ちにくくなるリスクがあります。だからこそ、今は「控える勇気」も大切なのです。
赤ちゃんの未来の健康は、毎日の離乳食の積み重ねから生まれます。「薄味=物足りない」ではなく、「薄味=素材の味を楽しむ力」と捉えて、ぜひ前向きに向き合ってみてください。
これからも赤ちゃんと一緒に「味覚を育てる時間」を楽しんでいきましょう。
【出典・参考文献】
-
厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08517.html -
厚生労働省 e-ヘルスネット「食塩と健康」
https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/food/e-03-004.html -
厚生労働省『授乳・離乳の支援ガイド(2019年改訂版)』
https://www.mhlw.go.jp/content/11908000/000496257.pdf





