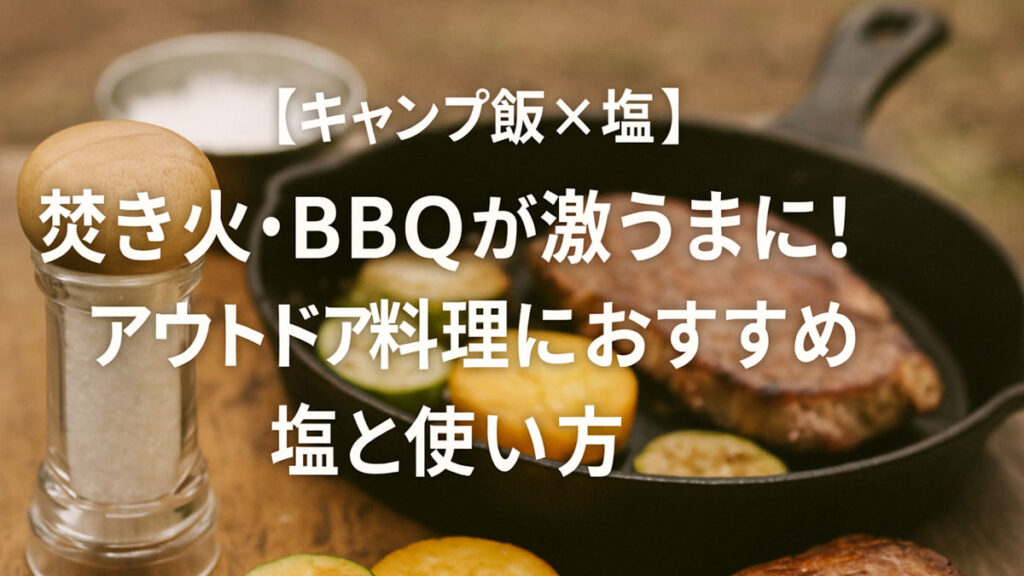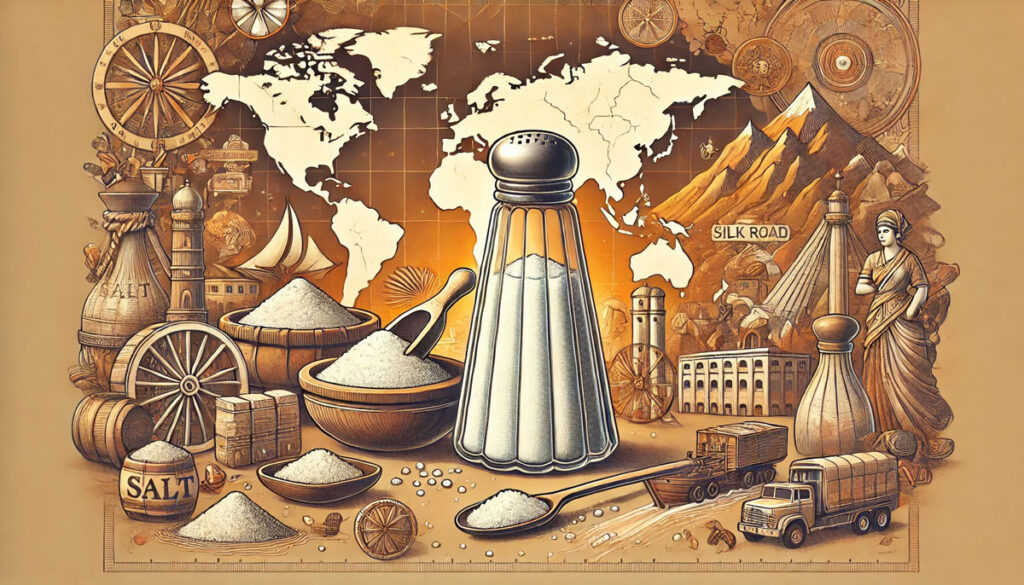「どの塩を選んでも一緒」と思っていませんか?
実はその塩、地球環境や社会に大きな影響を与えているかもしれません。
本記事では、塩の製造方法による自然への影響や、持続可能な製塩技術、日本国内で買える環境配慮型の塩ブランドをわかりやすく解説。
日々の買い物で環境に優しい選択をしたい方、エシカルなライフスタイルに興味がある方に最適な内容です。
塩を変えることが、未来を守る第一歩。この記事を通じて、今すぐできるサステナブルな選択を見つけてください。
なぜ今「塩」と「環境問題」が注目されているのか
私たちの生活に欠かせない「塩」
「塩」は私たちの食生活において基本的な調味料であり、食品の保存や発酵など、多岐にわたる用途で使用されています。また、医療や工業分野でも重要な役割を果たしており、例えば医療用の点滴液や化学工業における原料としても利用されています。このように、塩は私たちの生活に深く根ざした存在ですが、その生産過程が環境に与える影響については、これまであまり注目されてきませんでした。
近年、環境問題への関心が高まる中で、塩の製造方法やその環境負荷についての議論が増えています。特に、製塩過程でのエネルギー消費や二酸化炭素(CO₂)排出、さらには生態系への影響などが指摘されています。これらの問題を理解し、持続可能な製塩方法やエシカルな塩の選択について考えることが、今求められています。

塩の需要増加と環境負荷の関連性
世界的な人口増加や経済発展に伴い、塩の需要は増加傾向にあります。2020年の世界の塩の生産量を見ると、中国が約6,300万トン、アメリカが約3,861万トン、インドが約2,990万トンと、主要生産国が高い生産量を記録しています。
このような生産量の増加は、エネルギー消費の増大やCO₂排出量の増加を伴います。例えば、製塩過程での化石燃料の使用は、直接的なCO₂排出の原因となります。また、製塩のための海水取水や排水が海洋生態系に影響を及ぼす可能性も指摘されています。
さらに、世界全体のCO₂排出量は増加傾向にあり、2015年の約320億トンから、2040年までに350億トンを超えると予測されています。 このような状況下で、塩の生産に伴う環境負荷を軽減することは、地球温暖化対策の一環として重要視されています。
持続可能な製塩方法の開発や、環境への影響を考慮した塩の選択が、今後ますます重要となるでしょう。消費者一人ひとりが、塩の生産背景や環境負荷を理解し、エシカルな選択をすることが、地球環境の保全につながります。
製塩方法とそれぞれの環境への影響
塩は、さまざまな方法で製造されます。主に「海水塩」「岩塩」「湖塩」の3種類があり、それぞれ異なる自然環境への影響をもたらします。ここでは、それぞれの製塩法が持つ特性と、その環境負荷について詳しく見ていきましょう。

海水塩の取水・排水が海洋環境に与える影響
海水塩は、海水を蒸発させて塩を取り出す方法で作られます。日本を含む多くの沿岸地域で行われており、比較的低コストで大量生産が可能です。しかしその一方で、大量の海水取水と排水が周囲の海洋環境に深刻な影響を与えるケースもあります。
特に問題視されているのは、「高濃度の廃液」が海へ戻されることで、周辺の塩分濃度が上昇し、海洋生物の生態系が乱れることです。藻類の異常繁殖や、魚類・貝類の生息域の変化も報告されています。
また、製塩場の造成により海岸の自然環境が破壊されることもあり、持続可能な運用には慎重な管理が求められています。
岩塩の採掘と土地・生態系への影響
岩塩は、地中にある塩の鉱脈を採掘して得られます。主にヨーロッパ、アメリカ、中国などで盛んに採掘されていますが、この方法は大量のエネルギーを使用し、周囲の土地や生態系への影響も小さくありません。
地下深くから塩を掘り出すためには、大規模な機械と掘削作業が必要となり、これが土地の沈下や地下水の流れの変化を引き起こすことがあります。また、採掘後に放棄された坑道が土壌汚染や地盤沈下の原因となるケースも確認されています。
さらに、輸送に伴うCO₂排出も無視できません。遠方で採掘された岩塩を輸入することは、環境負荷の観点から再考すべき選択かもしれません。
湖塩と気候変動の関係
湖塩は、乾燥地帯の塩湖に自然に結晶した塩を収穫する方法で、主に中国やアフリカの内陸地域で生産されています。この方法は自然の蒸発作用を利用するため、エネルギー消費は少ない傾向にあります。
しかしながら、気候変動の影響を強く受けるという特徴があります。降水量の減少や気温上昇によって塩湖の水位が低下し、塩の採取量が不安定になるばかりか、塩湖の消滅が生態系に影響を与える可能性もあります。
また、風によって飛散する微細な塩分が、周辺の農地や居住地にダメージを与えることもあり、慎重な管理が求められます。
これら3つの製塩方法は、それぞれに利点と課題がありますが、共通して言えるのは「環境への配慮なしには成り立たない」ということです。消費者として、どのような方法で作られた塩を選ぶかを意識することで、未来の自然を守る一歩を踏み出せるかもしれません。
持続可能な製塩技術とは
地球環境への配慮が求められる中、塩の製造方法にも「サステナブル(持続可能)」な視点が必要になってきています。製塩は古くからある技術ですが、現代では自然環境と共存しながら塩を生産する技術の開発が進んでいます。ここでは、地球に優しい製塩技術として注目されている3つの取り組みを紹介します。

太陽熱を活用したエコ製塩
最も古く、そして最も環境負荷が少ない製塩方法のひとつが「天日塩」です。これは、太陽の熱と風だけを使って海水を蒸発させ、塩を結晶化させる方法で、主に気候の安定した乾燥地域で行われています。
この技術の最大のメリットは、エネルギーをほとんど使用せず、CO₂排出量も極めて少ないという点です。また、自然の力を最大限に活かしているため、生産過程での環境負荷が最小限に抑えられます。
ただし、天候に左右されやすく大量生産には向かないため、コストや安定供給の面で課題も残されています。
水資源を守るクローズドループ技術
近年注目されているのが「クローズドループ(閉鎖循環)型」の製塩システムです。これは製造工程で使われた水を再利用し、排水を最小限に抑えるシステムで、水資源の節約と周辺環境への影響低減を両立させる技術です。
具体的には、蒸発装置や濾過装置を連動させ、製塩後の濃縮海水を再利用可能な形で循環させます。この方法は主に都市型製塩施設や環境基準の厳しい地域で導入が進んでいます。
導入コストが高いため普及はまだ限定的ですが、長期的には経済的・環境的に大きな効果が期待されています。
国際的なエシカル認証とは?
製塩においても、「エシカル(倫理的)」な視点からの認証制度が導入されつつあります。たとえば、「Fair Trade(フェアトレード)」や「Rainforest Alliance(熱帯雨林同盟)」などの認証は、環境に優しい製法だけでなく、生産者の労働条件や地域社会への貢献も評価対象としています。
これらの認証を受けた塩は、消費者が環境と人権に配慮した製品を選ぶ手がかりになります。スーパーやネットショップでも「エシカル認証マーク」が付いている商品を見かける機会が増えており、選択の幅も広がっています。
環境負荷を最小限に抑えつつ、品質の高い塩を生産する技術の発展は、これからの社会に欠かせません。消費者が持続可能な選択を意識することで、生産者にも変化を促すことができます。「どのように作られたか」という視点を持って塩を選ぶことは、私たち一人ひとりができるサステナブルなライフスタイルの第一歩です。
私たちにできる「エシカルな塩選び」
環境や社会への配慮が求められる今、私たち消費者にもできることがあります。そのひとつが、日々の買い物で「エシカル(倫理的)」な製品を選ぶこと。特に塩のような日常的な商品こそ、選ぶ視点を少し変えるだけで、地球に優しい選択につながります。ここでは、塩を選ぶ際に意識したいラベルの見方と、日本国内で購入できる環境配慮型ブランドをご紹介します。

ラベルの見方と選び方のポイント
エシカルな塩を選ぶ際には、商品のラベルやパッケージの情報をしっかりチェックすることが大切です。特に注目したいのは以下の3つのポイントです。
-
製法の記載
「天日塩」や「自然塩」といった記載があるものは、太陽熱や風力を利用したエコ製塩の可能性があります。エネルギー使用が少なく、環境負荷が低いという点で評価されています。 -
原産地
輸送距離が短いほどCO₂排出が抑えられるため、「国産」や「地元産」と表示された商品を選ぶのも有効です。 -
認証マーク
「フェアトレード」「オーガニック」「エコサート」などのマークがある場合、環境保護や労働環境に配慮されている可能性が高いです。
こうした情報を確認しながら選ぶことで、単なる「価格」や「味」だけでなく、社会的な意義を持つ消費行動につながります。
日本国内で買える環境配慮型の塩ブランド
国内には、環境や地域社会への配慮を大切にする塩のブランドも増えてきています。以下に、エシカル視点で選ばれている代表的な塩ブランドをいくつか紹介します。
| ブランド名 | 特徴 | 原産地 | 製法 |
|---|---|---|---|
| 海の精 | 有機認証取得。太陽と風で自然乾燥 | 伊豆大島 | 天日・平釜併用 |
| 粟國の塩 | 昔ながらの製法を継承 | 沖縄県・粟国島 | 平釜・薪使用 |
| 五島灘の塩 | CO₂削減を目指す設備を導入 | 長崎県・五島列島 | 逆浸透膜+平釜 |
| あまみ塩 | 国産サトウキビの副産物から抽出 | 鹿児島県・奄美大島 | 廃熱利用 |
※すべて2024年時点の情報を元に構成。
これらのブランドは、製塩過程でのエネルギー効率、地域経済との連携、自然資源の保全などに力を入れています。スーパーや自然食品店、または公式通販などで購入が可能です。
私たち消費者がどの塩を選ぶかは、小さなことのようでいて、環境や社会への影響に直結しています。ラベルを見る習慣を持ち、エシカルな製品を手に取ることで、未来の地球を守る力になるのです。「おいしさ」だけでなく、「背景」も意識して選ぶことが、今、求められています。
まとめ|塩を選ぶことが未来を守る一歩に

塩は、私たちの毎日の食卓に欠かせない基本的な調味料です。しかし、その製造方法や背景にある環境負荷について意識を向ける人は、まだそれほど多くありません。今回のブログでは、海水塩・岩塩・湖塩それぞれの製造方法と環境への影響、そして持続可能な技術やエシカルな選び方について紹介してきました。
私たちが普段何気なく使っている「塩」にも、実は多くの選択肢があり、それぞれに自然や社会への影響があるのです。
特に、気候変動や資源の枯渇が進行する中で、今後の塩づくりには持続可能なアプローチが求められます。太陽熱を利用する天日塩や、水資源を再利用するクローズドループ技術、さらにフェアトレードなどのエシカル認証を受けた塩の存在は、環境と人権の両方に配慮した新しい価値観を示しています。
私たち消費者ができることは、「選ぶこと」です。商品ラベルを確認し、製法や原産地、認証マークに注目するだけで、より良い選択ができます。塩の価格や見た目だけでなく、その背景にあるストーリーにも目を向けることが大切です。
また、国産の塩を選ぶことで、輸送によるCO₂排出を抑え、地域経済の活性化にもつながります。これは環境問題への小さなアクションでありながら、持続可能な未来に向けた確かな一歩です。
このブログを通じて、「塩を選ぶ」というシンプルな行動が、地球や社会にやさしいライフスタイルの入り口になることを感じていただけたなら幸いです。
明日、スーパーで塩を手に取るとき、ぜひその裏側にある「環境への影響」や「生産者の思い」を思い浮かべてみてください。その一歩が、未来を守る大きな力になるかもしれません。
出典・参考文献情報
-
海水塩・岩塩・湖塩の製法と特徴|一般財団法人 塩事業センター
https://www.shiojigyo.com/ -
経済産業省|エネルギー白書 2023
https://www.enecho.meti.go.jp/about/whitepaper/ -
フェアトレード・ジャパン|フェアトレード認証の基準
https://www.fairtrade-jp.org/ -
環境省|気候変動への取り組み
https://www.env.go.jp/earth/cc/